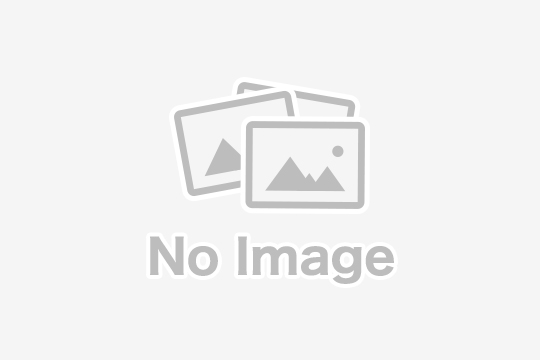7:42 そこで神は顔を背け、彼らが天の星を拝むままにしておかれました。それは預言者の書にこう書いてあるとおりです。『イスラエルの家よ、/お前たちは荒れ野にいた四十年の間、/わたしにいけにえと供え物を/献げたことがあったか。
7:43 お前たちは拝むために造った偶像、/モレクの御輿やお前たちの神ライファンの星を/担ぎ回ったのだ。だから、わたしはお前たちを/バビロンのかなたへ移住させる。』
ステファノによれば、偶像崇拝は、神の刑罰の原因であると同時に、神の刑罰そのものでした。神は御自分を認めようとしない者たちを、無価値な思いへと引き渡されるのです(ローマ1:28)。ここで、「天の星を拝む」とありますが、これは後にイスラエルの王国時代に盛んだったものです。
金の子牛に見られる偶像崇拝は、その後のイスラエルの歴史においても無くなることはなく、むしろ盛んに行われていたのです。その罪を暴き、神に立ち帰るように呼びかけたのが、預言者たちでした。ここでステファノは、預言者アモスの言葉を引用しています。
このステファノの言葉によれば、荒れ野の40年間においても、イスラエルの家は、主なる神にいけにえと供え物を献げたことはありませんでした。もちろん、彼らは動物犠牲をささげておりましたが、それは主なる神に献げていたのではないというのです。それでは、一体に何にいけにえや供え物を献げていたのかと言いますと、お前たちは拝むために造った偶像、モレクの御輿やお前たちの神ライファンの星を担ぎ回っていたというのです。
これは、実際、荒れ野において、モレクの御輿やライファンの星を担ぎ回ったということではなくて、主なる神を礼拝しながらも、彼らは造られたものに常に心ひかれていたということです。ちょうど、シナイ山において、先祖たちが、エジプトを懐かしんだように、彼らの心は造られたもの、目に見えるものにひかれ続けていたのです。
そして、その礼拝は、神に仕えるため、神を喜ばせるためではなくて、自らを喜ばせるためでした。それが「拝むために造った偶像」という言葉の意味するところです。礼拝それ自体が目的化され、その対象である神が見失われるときに、その礼拝はもはや真の礼拝とは呼ぶことはできないのです。そして、バビロンへの捕囚も、主なる神へのまことの礼拝が失われていたがゆえの、神の刑罰であり、神の訓練だったのです。
祈り
天の父なる神様、イスラエルの人々が、「私たちは神に従います」と言いながら、実際には様々な目に見える偶像に心を奪われ、神がお遣わしになった預言者のことばを聴こうとせず、かえって預言者たちを迫害したのです。ステファノは彼らが悔い改めて神に立ち帰るようにこの説教をしているのですが、実際にはステファノも殉教の死を遂げることになりました。私たちにいのちを与え、育み、死から命へと導いてくださるあなたに心を向けて生きることが出来ますように。
イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。