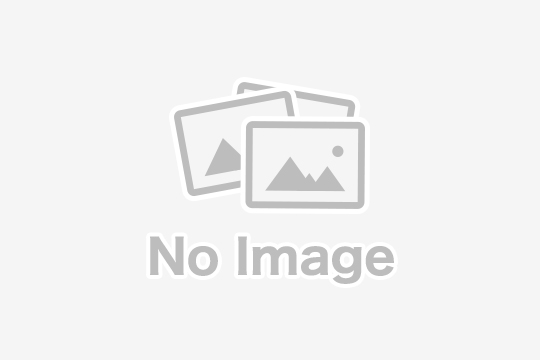6:1 そのころ、弟子の数が増えてきて、ギリシア語を話すユダヤ人から、ヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは、日々の分配のことで、仲間のやもめたちが軽んじられていたからである。
初代教会は、すべての物を共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて、皆がそれを分け合っていました。そのために信者の中には、一人も貧しいものがいなかったのです。しかし、今日の御言葉には、日々の分配のことで、不和が生じたことが記されています。それは、ギリシア語を話すユダヤ人とヘブライ語を話すユダヤ人という教会を構成していた二つのグループの不和でした。
ギリシア語を話すユダヤ人とは、ギリシア語を日常語とする外国生まれのユダヤ人のことです。ローマ帝国に離散していた、ディアスポラのユダヤ人が、エルサレムに帰って来ていたのです。また、ヘブライ語を話すユダヤ人とは、これはパレスチナの地方で生まれ育ったユダヤ人。ヘブライ語、より正確に言えばアラム語を日常語とするユダヤ人のことです。
どちらもユダヤ人ですが、ギリシア語とヘブライ語ですから、どうもコミュニケーションがうまくとれなかったようです。ギリシア語を話すユダヤ人は、もうほとんどヘブライ語、アラム語が分からなくなっていました。また、ヘブライ語を話すユダヤ人も、多少はギリシア語が分かったと思いますが、皆が皆、ギリシア語にそれほど堪能であったわけではなかったと思われます。
ですから、この二つのグループは、おそらく別々に集会を持っていたのではないかとさえ考えられるのです。ギリシア語を話すユダヤ人は、そのユダヤ人だけで、ギリシア語に訳された旧訳聖書を読み、礼拝をした。また、ヘブライ語を話すユダヤ人は、ヘブライ語で旧約聖書を読み、アラム語で礼拝をした。
これは、言葉が違う以上、致し方ないことであったと思います。そして、言葉、言語が違うことは、生まれ育った環境が違うということでもあって、その考え方も違う所があったことが考えられます。例えば、エルサレム神殿について、ギリシア語を話すユダヤ人とヘブライ語を話すユダヤ人では、少し異なった見方をしていたようです。
3章を見ると、ペトロとヨハネが午後三時の祈りの時に神殿に上っていたことが記されていました。また、使徒たちは神殿において集会を開き、そこで伝道していました。ヘブライ語を話すユダヤ人である使徒たちは、神殿を大切に考えていたことが分かるのです。
けれども、ギリシア語を話すユダヤ人の代表的な存在であったステファノの説教をお読みいただくと分かりますように、そこでは、エルサレム神殿そのものが、あからさまに疑問視されています。これは、ギリシア語を話すユダヤ人とヘブライ語を話すユダヤ人の間に、言葉だけではなく、その考え方にも、違いがあったことを教えられています。
祈り
天の父なる神様、ギリシャ語を話すユダヤ人たちとヘブライ語を話すユダヤ人たちとの間で意思の疎通がうまくできないで、ギリシア語を話すユダヤ人から、ヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出てきました。使徒たちはこのような問題に対処するあり方を検討することになります。そこで使徒たちの他に執事と言われる働き人が選ばれるようになりました。このように教会のあり方がより現実に即したものとなり、様々な人たちがともに主を見上げて主の教会を立て上げていくようになったことを感謝いたします。
イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。